僕が前を向き、再び歩き始めてから少し経った。
攻略はメンバーの予定が合わず、あまり進んでいなかったものの、僕は僕で木人討滅戦とヴァイパーでのコンテンツ参加を繰り返していた。
やることやできることが明確になっていれば迷わないし、退屈にもとれる日々の積み重ねも、仲間への貢献ができると考えると楽しい。
そして武器といくつかの装備が更新できて、ついに木人を割ることができた。

ただ木人を割る。
レイドに臨むのならやって然るべきことだ。コンテンツ参加の最低ラインと言うことだってできる。ここまできてようやく、少なくとも今までは気負いがあってやっていたんだと気づく。木人が割れてこんなに嬉しいことは初めてだ。
そんな日々を送る中で、僕が病院へ行った帰り道でのこと。
真っすぐ最短で帰らずに、ついでに散歩もしようといつもの散歩コースへ入って5分程歩く。
バス通りから路地を入って、路地と路地をゆるいカーブで繋ぐ奥まった道。車がすれ違えるほどではないけれど狭くもない、いわゆる抜け道。左右は住宅で、人通りも多くはないが全くないわけじゃない。そんな道を歩いていると、遠くの電柱の下で人が寝転がっているのが見えてきた。
遠目には職人のおっちゃんが休憩でもしているんだと思った。近くで工事をしていたし、仕事柄そんな人々とも接する機会があるから行儀は良くないかもしれないけど全く経験のない状況ではない。そして何よりすれ違う人々があまりにも普通だったから、まさか人が転んで起き上がれずに倒れているなんて思いもしなかった。
異変に気付いたのは遠目にその人を確認してから10m程歩いた時で電柱まで30m程だっただろうか。目の悪い僕でもどうやら職人のおっちゃんが寝ているのではないということに気付き、同時に人が倒れているということは転倒か発作だと直感する。
こんなことがあるのかと思った。
そして同時に今すぐそこですれ違った人々は放っておいたのかよと思った。視界に入る犬の散歩をする女性、僕の向かいから歩いてきて寸前ですれ違ったスーツの男性、鼻歌交じりの自転車の男性もいた。必ず目には入っている位置関係だ。人間の、特に僕の記憶なんて曖昧なものだというのは理解しているけれど、どこか冷静にあんたら何もしなかったのかよと憤りさえ感じた。
その憤りは、倒れている人を助けない奴らという侮蔑よりも、僕が手を貸すしかないじゃないかというどこかそんな人々と同類じみた責任転嫁で、自分の身を一番に案じるようになってしまった自分に気が付き小さく失望した。
助けることで言いがかりをつけられたり、面倒に巻き込まれても嫌だ。かといって見て見ぬ振りもできない。いっそ回れ右をして逃げ出してしまうか。
僕は辛うじて歩くペースを保ったまま道を進む。一歩一歩、神の審判を受けに行くような気分だった。
神様か仏様か、僕にはわからないけれど、前を向き再び少しづつ歩き始めた僕を試し計っていて、それでいて全てを見透かされているようにも感じた。
10m、まだ引き返せる。
7m、覚悟が決まらない。
5m、そもそも僕には何もできない。もういいか。
3m、そっと口から息を吐く。
「大丈夫ですか?」
覚悟を決めたというよりは、諦めたように言葉を振り絞った。
顔を歪めているのか?意識はあるっぽい。よく見ると小さく手足をうごかして足掻いているみたいだ。そんなことにも気が付かないなんて…。
僕の言葉に返事はないが、顔がこちらに向く。年の頃なら五十代くらいだろうか。ぼさぼさで白髪交じりの長い銀髪に毛玉の目立つくたびれた服。言い方が悪いけれど、小汚い身なりという印象を受けた。
電柱の下なので車の通行の邪魔にはならない、狭くはない道なので安全面は大丈夫だろう。倒れたときの状態が分からない。動かさないほうがいいんだったっけ?救急車を呼ぶべきか判断できない。#7119が妥当か?それにしても現状把握はしなければ。
「僕の声が聞こえますか?」
ポケットから携帯を取り出しながら再度声をかける。相変わらず返事はなかったが、小さく頷いてくれた。目も合っている。左手側に杖があり、右手は拘縮しているのか肘と手首が曲がり胸の前に密着している。
あ、片麻痺か。左脳って言語障害だったっけ。
「失礼、右手側が利かないです?」
苦い表情で頷く。やっぱりそうだ。
「助けになれることはありますか?」
頷いて返事が返ってくる。
「救急車を呼びますか?」
頷かない。
「痛いところはありますか?」
腕を動かして返事が返ってくる。腕か。動かせはするのか。
「頭は?」「打った?」
頷かない。本当か?打った直後で痛みが出ないだけじゃないか?
「連絡の取れる家族とかいますか?」
頷く。
「携帯ありますか?」
頷かない。
「番号わかりますか?」
頷かない。
助けを求められる人はいるけど連絡手段がない。どうしたもんか。というか遠出はしないよな普通に考えたら。
「家は近いですか?」
頷く。
となれば大まかな場所と色くらいでいいから聞いて片っ端からピンポン鳴らして聞くしかないか。
「どうしたいですか?私が家探してくる?」
頷かない。何かを伝えたいのか腕を上下にゆするように動かしている。
「立ち上がりたい?」
頷く。大丈夫かよ…。やりとりでそこそこ時間が経ってるはずなのにこんなときに誰も通らない。これで起こして何かあったら恨まれるんだろうなあ。
「痛みは?歩けますか?」
初めて大きく頷いた。もしかするとここで倒れていることが嫌なのか。それにしたって命は何にも代えられない。一般人が素人判断で動かすもんじゃない。見返りなんて何もいらないけれどリスキーすぎる。
迷い動揺する僕を急かすように、彼女は再び腕を動かした。起こしておんぶするか支えながら家までいくしかないか。
「失礼、体に触れますね。」
彼女が頷くのを確認すると僕は後ろに回って、肩と首を支えながら彼女の上体を起こした。
後ろからなら尻もちをついても僕が下敷きになれるかもしれない。体で背中を支えながら腕をできる限り組んでもらう。わきの下に腕を回して腕を掌で掴む。
「せーので起こします。一緒におじぎしてください。」
合図と同時に体を起こす。しまった。起こしたはいいけど電柱にはギリ届かないかも。支えながらゆっくり状態を変えるしかないか。そんなことを考えているとキキっとブレーキ音が鳴った。
「大丈夫ですか?どうしました?」
僕と同じか少し年上くらいの男性が僕の視界に現れながら聞いてくれた。
「この方転んじゃったみたいで、起こしたんですけど、手を貸してもらえますか。」
さすがに男手二人となると安定したもので、そこから難しいことはなかった。
杖を渡して、状況を説明していると、後ろから五十代くらいのご夫婦もやってきて、方向が一緒みたいなのでお送りしますと言ってくれた。
この状況の先が見えたことと、葛藤があったものの自分が逃げ出さずに居られたことに安堵した。最高の対応ではないにせよ、困っているであろう人を放っておかずにいられた。
「ありがとうございます。ではおまかせします。」
僕は自転車の男性とご夫婦に会釈すると、倒れていた彼女を何気なしにそっと見た。
彼女は、怒気と恨みが少しづつこもった目で僕を睨んでいた。感謝をされたかったわけじゃない。それでも、まさかそんな目で見られると思っていなかったし、感謝の形が握手か何かは分からないけど、感謝くらいは伝えられるのかなといつのまにか勝手に思ってしまっていたので僕は面食らった。
「すみません。」
僕はちいさな声で一言呟いて。逃げるように早歩きでその場を去った。
きっと僕の気のせいだろう。僕が勝手にそう見えただけで、感謝を伝えたかっただけかもしれない。それに身に降りかかってしまった不運にやりきれない気持ちだってあったのだろう。お腹だって空いていたに違いない。
割り切ろうとしたが、小さな彼女の、怒気と恨みを孕んだ目が僕の頭から離れなかった。
こんなときに無知が恥ずかしくなる。でもこんな状況で最善の処置が咄嗟にできる人なんてこの世界にどれだけいるんだろう。最善の処置かどうかはわからないけど、僕にできることはしたと願う。
蛇に睨まれた蛙はこんな気持ちなんだろうか、僕は急に不安で体が熱くなるのを感じた。放したいのに手放せない、いつかどこかで感じたことのある、身に覚えのある熱さだった。
こんなことは、ブラインド攻略に関係ない。
理解しているものの、僕の思考は連続して再生されるカットシーンみたいに長く、そして螺旋のように渦を巻いた。
ここが画面の前で、君が目の前にいたら良かったのに。倒れている彼女を僕じゃなく、君が見つけていたらどんなに良かっただろう。
誰かを助けるのに理由はいらないけれど、僕は自分を守る理由を一番に考えてしまうような人間になったんだ。
若き日の自分なら、人が倒れていると気づいた時点で小走りで近づいて、何の保身も利害も考えずに目の前の人を助けることだけを考えられた。若く、青く、愚かな僕は良い人だった。
今までFF14で倒れた人やモンスターに襲われている人をいくらでも助けてきたのに、リアルな僕は転んで起き上がれない人に、手を貸すことすら満足にできないという現実を突き付けられた。
僕にはフレッシュさも、ひらめきも、分析力も、コンテンツ攻略の瞬発力もない。
こんな僕になにができるんだろう。僕のしてきたこと、したことは何だったんだろうか。
例年よりだいぶ早い梅雨が世間を騒がす頃に、前向きになって歩き出したはずの僕は、下を向き立ち止まるどころか、再び螺旋階段を落ちるように、簡単に今までの取り組みをやめた。

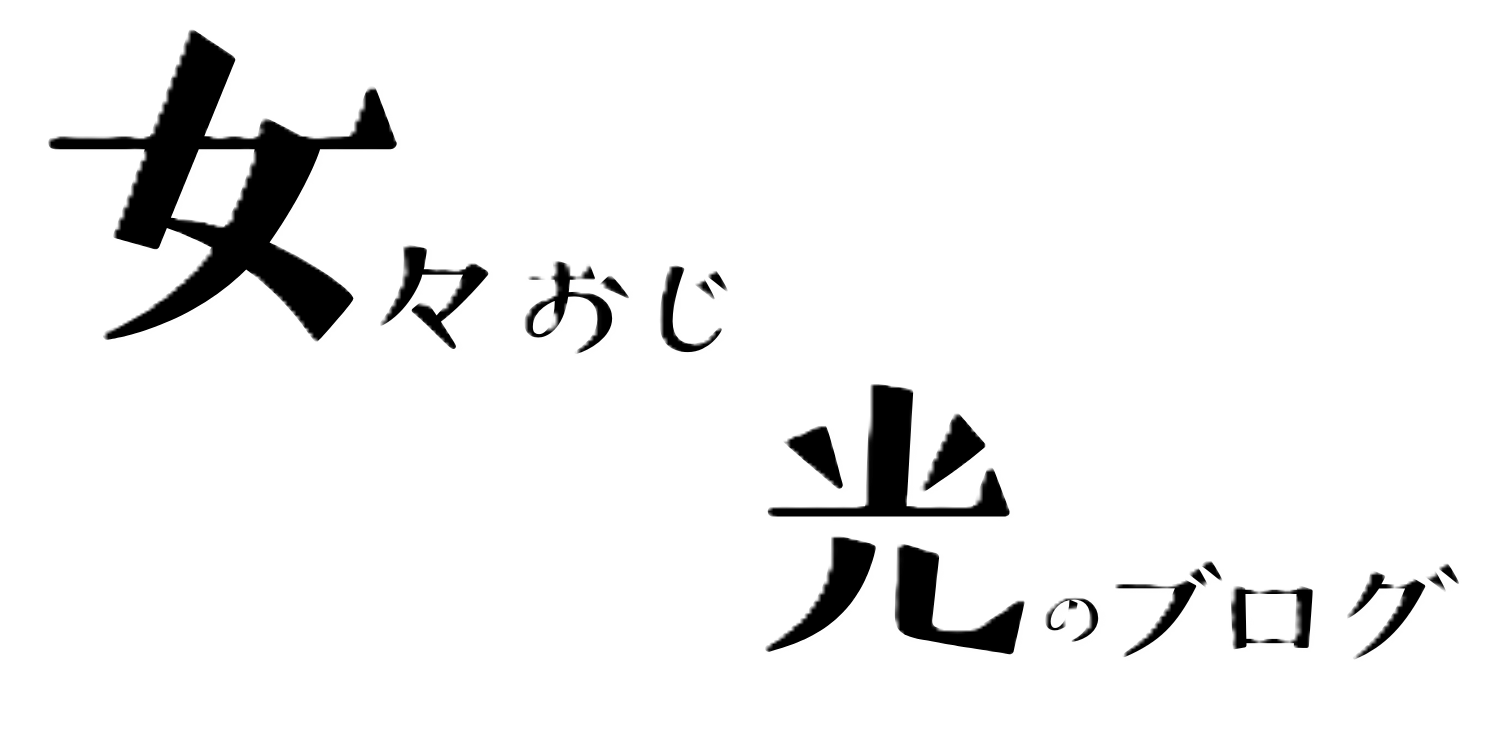



コメント